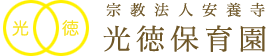345歳クラスでは、おえかきを楽しむ姿が多く見られます。小さい頃は何も考えず自由に描くことを楽しんでいましたが、今は上手に描きたいとの思いやこれを描きたいという思いもでてきました。その中で描きたいと思ったものを頭の中に浮かべ、自分なりに形にしていくことができる子もいれば、どうやって描けば描けるのか?と悩んで描けなくなってしまう子もいます。
一回描いてみては、納得がいかず消しゴムで消してまた描いてみたり、悩み過ぎてしまい鉛筆を持ったまま時間が経過してしまっていたり、自分では難しいのでお友だちに描いてもらう子など様々な姿がありました。
本来は子どもたち自身が描きたいものを自由に描いて楽しんで欲しいと思い、描き方などは特に知らせていませんが、絵を描いてみたいけど、どうやって描けばいいのか分からない姿が長い期間続いていた為、描き始めのヒントになるように子どもたちの好きなキャラクターの描き方を出してみました。



出してみると、嬉しそうに手に取りジッと見ている子、見ながら少しずつ真似をして描いてみる子がいました。
真似をして描いていくうちに、顔の輪郭はこんな風に描けば描けるんだ!髪の毛はこうやって描くんだ!と描きながら発見していく姿が見られました。いつもは自信が持てず、絵を描いている途中で友だちや先生に見られないように手で隠していた子も、「見てみて顔描けたよ〜」など描きながら他のお友だちに見せる姿や描いていて楽しそうに笑顔になってくる姿が増えてきました。
何度も描いていくうちに自信にも繋がり、今では何も見ないで自分なりに考えて描くことを楽しんでいます。
お友だちと色々な物語を作りながら描いたり、個々に描きたいものを描いたりこれからも色々な絵を楽しんで描いて欲しいです。



保育士 M.Y